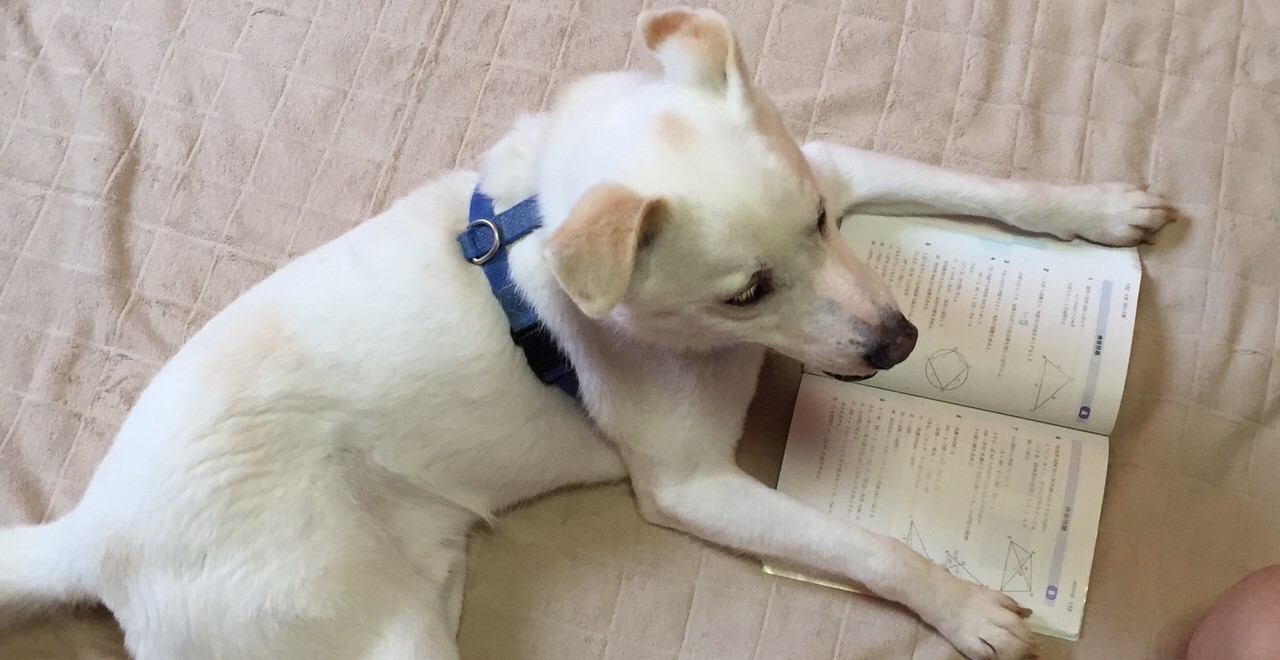研究日記1
ここ1か月の研究の足取り及び思いをつらつらと書きたいと思う。
なかなか研究テーマが定まらないというのが現状である。漠然としたテーマは現時点では固まってきていて,それは脆性破壊(ばきっとこわれるやつ 岩とか)における不安定な挙動は延性破壊(壊れる前に伸びる 餅とか?)ではどのように安定化されているんだろうか,というモノなんだけど,この問いを解決するには何を計算してどういう結論が出ればいいのかがわからない。
また,数値計算の結果もあまり芳しくない。上のテーマに関して数値計算で何かやりたいんだったら,パラメータ変化で脆性と延性をどちらも表現できるモデルを扱う必要がある。先行研究でそうしたモデルの一つは提案されていているので,それを参考に今自分が扱っているモデルでもそのような挙動を見出したいんだけど,うまくいかない。次元が違う(先行研究は2次元の板みたいな系で,自分がやってるのは3次元)ので有限サイズ効果のせいかもしれん。となると,三次元でサイズを増やすのはめんどくさいし,どうしようかなぁ。
しかし,全く進歩がなかったかというとそんなことはない。論文の読み方というものが(やっと)身についてきたのである。最初のころは「読むって言ったってどうしたらええねん」という感じだったが,適当に読み漁っているうちに自分の問題意識と照らし合わせて「ここ重要っぽいぞ」とか「ここは読み飛ばせばいいわい」みたいに,内容に強弱をつけながら読めるようになった。そんなもん卒研で身に着けとけよという話だが,今にして思うと卒研の取り組み方は数本論文を読んで追計算しました的なお粗末なモノだったのでしょうがない。最近は論文を読むごとに「じゃあこんなの計算してみたら面白いかな」というアイデアがぽこぽこ出てきて楽しい。数値計算いろいろ試しつついろいろ読んで勉強すると,上で書いた「ふわっとした疑問を解決可能な問題のレベルまで落とし込む」っていうのができてくるのかもしれない。
それと,新しく好きな研究者ができた。「これ面白そうだなー」と思って開いた論文の著者がことごとくその人だったのである。google scholarをみてみると,「複雑系」(ちょっと古いか?)という大枠の中で破壊現象から生物分野まで幅広く研究をしていた。書いてる論文もどれも面白い。もし博士課程に進んだら(俺と普段話してる人からしたらいつまで留保してんねんという感じだろうが),「つながり」とか「安定・不安定」みたいに,追求したい世界観をはっきり持ったうえで,この人みたいに幅広い分野に首を突っ込んでみたいなあと思った。
超域の面接も先日終わった。カデットの時とは違い,「俺なんか絶対受かるにきまっとるやんけ!」という感じじゃないので,肩の力は適度に抜けている。受かったら博士課程進学における経済的心配が軽くなるのでここで決めきりたいが,仮に落ちてもM2向けのカデット(今冬,時期的には悪くない)と学振及びDからの超域(決まるののはM2の終わりなのでこれにかける時点で経済的不安を抱えつつ24卒を諦めることになる,ちょい時期悪)があるので,経済的支援の手札がすべてなくなるわけじゃない。結果は9月中旬らしいので,徒然なるままに,少しそわそわしながらその時を待とうと思う。
まとめると,表面的には何も進んでいないが,水面下では構想が少しづつ固まってきており,それなりに楽しく研究活動ができている。私生活の方でもいろいろ新しいことに手を伸ばしつつ,トータルでよい精神状態を保ったまま日々を過ごしていきたい。